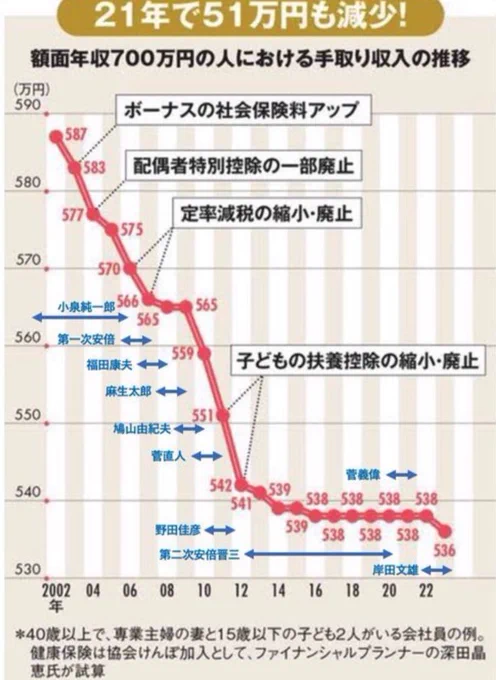東京経済大学の財政学者。「有國有家者 不患寡而患不均 不患貧而患不安 蓋均無貧 和無寡 安無傾」季氏第十六より。そういう学問をしたい。 「石を拾うことはあっても 珠を捨てること勿れ」 そういう教育をしたい。
南千住 国分寺
Joined July 2012
- Tweets 43,693
- Following 2,464
- Followers 5,960
- Likes 58,529
佐藤一光 retweeted
この方のポストを遡って読み漁った。最初は「この人の子供3人とも障害児なの?」と事情もわからず不思議に思ったけど、読んでいるうちに病院に置いてきぼりにされた障害児たちを養子に迎えているんだと分かった。付き添い入院8ヶ月交代なしを読んだ時は震えた。支援したい。欲しい物リスト出してほしい
佐藤一光 retweeted
日銀消費活動指数が公表されておりますが、9月自体は消費は増加したものの、7−9月期でならせばマイナスです。消費はマクロで見ればあまり良くないという結果に見えます。
ただGDP上の個人消費については家計調査などの統計も含めて推計されますが、家計調査などはマイナスの伸びではありませんのでGDP上の個人消費はぎりぎりプラスというぐらいの結果になってもおかしくないように思います。もちろんマイナス予想をする専門家もいます。
いずれにせよ個人消費の基調が強まっているという状況にはないという結果になるように思います。7−9月期のGDP上の消費がプラスか、マイナスか、という点はテクニカルな要因も含まれますので判断が極めて難しいです。
そしてこの記述は正しかった。
ITバブルがはじける直前の経済白書
「最近の情報通信技術の長期的なインパクトはまだ十分明らかではないが、過去の蒸気機関、電力、自動車などに匹敵する(1)大きな技術革新の波である可能性が高くなってきた」
平成12年度年次経済財政報告 新しい世の中が始まる
平成12年7月
cao.go.jp/j-j/wp/wp-je00/wp-…
上げ相場のときは外国株が。
下げ相場のときは国内株か債券が。
分散投資とはいうけれど、全て外国株に突っ込んでいた方がリターン大きかったのではないか。
#GPIF は、長期的な観点から国際分散投資を実施しています。主要4資産の代表的な指数のリターンの推移をご覧ください。毎年値上がりの大きい資産クラスを当て続けることは困難ですが、過去データでは #分散投資 をすることで、長期的には安定した収益を得られています。gpif.go.jp/gpif/diversificat…
外形で美人投票しなければならないので
どうしてもこういう事例が後を立たない。
唯一の"田久保派"市議に経歴詐称の疑い 航空自衛隊出身で「パイロット」とホームページなどに記載も実際は訓練で脱落 本人はSNSで釈明も空自は「パイロットになれなかった人」
news.yahoo.co.jp/articles/45…
4年前の質問なので、質問者さんがどうなったのか、、、
もしかすると同じようなことで悩んでいる人がいるかもしれませんので、私なりのアドバイスをしたいと思います。
ポイントはふたつ。
どんな医師になりたいか。医師の大部分の業務ではコミュニケーションが必要です。高校はコミュニケーションを学ぶ場です。その学びの機会を逸してしまう。ハードワークとコミュニケーションとの両立が求められます。
どんな人生をら歩みたいか。
人生の半分は他者で構成されます。つまり、友人たちがなさあなたの人生を構築する。高校から大学にかけてが人生で最も豊かに、利害関係なく人間関係を構築できるチャンスです。逸するなかれ。
2000年代は白物家電から薄型テレビの分野で中国の輸出がディスインフレ効果があった。
これが2020年代にはBEVを通じて新しい分野にも波及し始めている。
家電産業の転換で日本は失敗した。
自動車産業で同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。
日本銀行、中川審議委員の講演が行われました。需要項目別からの日本経済の現状、物価の見通し、それを踏まえた金融政策の見通しにつきまし丁寧に説明されており、大変勉強になるご講演でございました。
特に金融政策に対する目新しい材料はありませんでしたが、1点個人的に印象的だったのが中国による米国以外への輸出拡大がリスク要因として指摘されていた点です。これはおそらく推察になりますが、デフレ輸出の点に言及されたのだと思います。中国の過剰生産によるディスインフレの経済状況下、輸出価格の低下によって輸出が拡大することで中国製品の輸入が増えた国の場合、現地企業への打撃(価格競争による収益悪化や生産低下、投資減などでしょうか?)が考えられるということと思います。
特に中国の貿易統計を見ていますと自動車輸出の伸びが著しく、定性的な情報を加味しますと、アジアなどへの電気自動車輸出や部品が底堅く推移しており、現地への企業進出増加に伴う中国からの輸出増も連動して来ている面があると思います。タイなどで日本現地自動車メーカーが現地市場で勢いがないといった声も聞いていたりします。中国の製造業での影響力は近年非常に大きくなっており、日本から中国への輸出も増えなくなって来ております。
日本経済へのリスクという意味では、中国からの製品流入増による価格競争激化に加え、かつて中国に多く輸出していた財が伸びなくなる(中国製品の競争力増加による内製化)ことによる輸出の下押しという面もあるように感じました。
実質金利がマイナスになっているというのはひとつ利上げが求められる背景にある。
他方で、足元が投資過剰なのかどうか。もっとも金利に反応する住宅市場が加熱気味なのか?
物価のメカニズムとして需給・賃金・期待を上げているが、賃金と期待に政策金利をもって働きかけることはできない。
日本銀行から10月会合の主な意見が公表されました。
序盤の景気の認識については明らかにタカ派的認識が増えたように思います。トランプ関税による悪影響はもう限定的となり、日本景気への下押し圧力ももう小さいだろうとの見方が多かったと思います。
ただ金融政策の箇所については、思ったよりは不確実性に言及されていた印象です。米国経済の不確実性と、高市政権の経済政策の不確実性の2点が挙げられています。後者は単に発足したばかりということが理由と思います。
12月会合の利上げの有無については、国内経済については特に問題なしと考えている委員が多いと見られ、米国次第、為替次第に加え、高市政権の政策内容次第では利上げもあり得るとしか言いようがないと思います。高市政権については、首相と植田総裁のコミュニケーションがいつ取られるのか、その結果、利上げに対する共通認識がどう生まれるか次第ではないかと見ています。
実質金利が大幅マイナスという認識や、不動産など資産価格への言及、基調的物価よりヘッドラインを重視した判断など、明らかにタカ派的言及は出ていますが、政策判断はなお米国経済次第が第一で、次いで為替といったところでしょうが、高市政権側の利上げ認識も鍵を握ると見られます。
一方で12月会合に利上げがされれば多少はサプライズにはなりますが1月会合までの利上げはコンセンサスになりつつありますので、12月会合に利上げをしたとしてもあまり株価には響かなそうに思います。むしろ1月会合までに利上げをしなかった場合の影響の方が大きそうです。これはテールリスクシナリオと現時点では見ています。
菅野候補の重点政策
①外国人問題:国民健康保険の未納対策・民泊規制を徹底
②防災:家庭の防災用品購入を補助するクーポン
③子育て:子供たちの郷土愛を育み、家庭的保育を推進
これが受けた面もあろうし、参政党の勢いもあろう。若さが評価された側面も。
参政党29歳トップ当選 東京・葛飾区議選「日本人ファースト」主張(朝日新聞)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/ca…
佐藤一光 retweeted
Journal of Economic Perspectives最新号は、「日本の債務パズル」論文から始まり、「東アジアの奇跡」シンポ論文、バーナンキの大恐慌再考論文、インベンズらの「Lalonde(1986)から40年」論文と、読みどころがたくさんありそう。
aeaweb.org/issues/826
散々無駄だと評されている政策
火中に栗を投げ入れて拾いに行った。
うわぁ。おこめ券w
総合経済対策の検討状況が判明 コメ価格の対応に向け「おこめ券」の活用を盛り込む方向
newsdig.tbs.co.jp/articles/-…
だったら一律2万円配った方がマシだったのでは?
総合経済対策の検討状況が判明 コメ価格の対応に向け「おこめ券」の活用を盛り込む方向 | TBS NEWS DIG (1ページ) newsdig.tbs.co.jp/articles/-…
佐藤一光 retweeted
個人的感想にすぎないが、「働ける人がたくさん働ける社会」という考え方は、「職場にはいろんな人がいるので、それを考慮した仕組みを作る」という考え方とバッティングしてしまうことも多そう
上手く環境構築できる職場もあるだろうが、組織や人事の実務家や専門家の肌感覚としてはどうなのだろう
佐藤一光 retweeted
働き方改革は「いま働いている人の労働環境を改善する」という視点に加えて「これまでそこでは働けなかった人も働ける場にする」という視点を大切にしてほしい
チャレンジングだが、「職場にはいろんな人がいるのでそれを考慮した仕組みを作る」という「合理的配慮」は、障害の有無関係なく適用できる
これをヴァーグナーの法則と呼ぶ。この法則は、経済が成長するにつれて、国民所得に占める政府支出の割合が長期的に増大する傾向を示すものとされる。
ヴァーグナーは、政府支出拡大の要因として主に3つの論拠を示した。
①経済発展に伴い社会が複雑化することで、法秩序の維持や財産権保護のための行政需要が増大する。
②工業化の進展により教育や文化といった公共サービスへの需要が高まる。
③都市化や産業化に伴い、上下水道、交通インフラなど公共投資の必要性が増大する。
これは150年くらい前の議論なのだが、現代では医療、介護、子ども・子育て、年金といった社会保障制度が発達しているため、よりその傾向が強まっているといえよう。