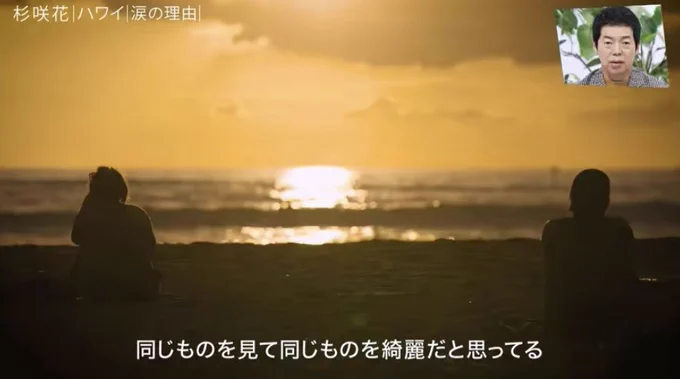Joined April 2025
- Tweets 27
- Following 15
- Followers 3
- Likes 0
な retweeted
マッキンゼーがAIの現在地を示す、衝撃の2025年版レポートを公開しました。
多くの企業がAIを導入しつつも、その真価を発揮できていない「企業AI劇場」とも言える実態が浮き彫りになっています。
完全無料です。
AI導入の成功と失敗を分ける10の重要なポイントをまとめました。
1. AI導入の実態とパイロットからの脱却
企業の90%がAIを利用しているものの、67%は未だパイロット段階に留まっています。これは「企業AI劇場」と揶揄される状況です。
2. AIエージェントの導入状況
企業の62%がAIエージェントを実験中で、本格導入は23%。特にテクノロジーとヘルスケア分野で導入が進んでいます。
3. AIのインパクトギャップ
64%の企業がAIはイノベーションに貢献すると信じている一方、EBIT(金利税引前利益)の増加を実感しているのは、わずか39%に留まります。
4. 高い成果を出す企業の戦略
上位6%の高性能企業は、POCに留まらず、ワークフローの再構築、成長目標の設定、そして実際の予算を投下するなど、より大きな視点でAIに取り組んでいます。
5. リーダーシップの重要性
AI導入をリーダー自らが主導する企業は、AIを大規模に展開できる可能性が3倍も高くなります。トップのコミットメントが不可欠です。
6. 成功企業のAI活用法
成功企業は、単に作業を高速化するだけでなく、AIを使って「働き方そのもの」を変革しています。業務の再定義が鍵を握ります。
7. パフォーマンス測定基準の違い
一般的な企業が「効率性」を測るのに対し、トップ企業は「AIエージェントの行動速度」を測定します。指標の違いが成果の差を生んでいます。
8. リスク管理の現状
51%の企業がAI導入で予期せぬ問題(特に不正確さ)を経験。リスク管理の重要性がこれまで以上に高まっています。
9. 労働力への影響の不確実性
AIによる人員削減を予想する企業が32%いる一方、成長を予想する企業は13%。労働力への影響は、まだ見通しが不透明です。
10. AI導入はまだ初期段階
AIの導入は主流になりつつありますが、レポートは「真の変革はまだ始まったばかり」だと結論づけています。
な retweeted
Twitterでは銀座で単価6-7,000円のまともな店なんか無いって言ってきてるキチガイがいるけど、この辺りの店普通にアポに使えるし美味いからな。
お前らいつも何食ってんだよ。
鳥ばか一代とかマジおすすめだぞ。
総合商社マンおすすめの銀座カジュアルデートで使えるお店貼っとくわ。
な retweeted
シリコンバレーのプロダクトマネージャーの知見が詰まった資料が凄い。PdMに必要な視座、コミニュケーション、経営者感覚、KPI、時間術、ロジカルシンキング、クリティカルシンキング等の項目がわかりやすく言語化されている。
こちら👉
speakerdeck.com/sonehara/pmc…
世界で1500万回以上再生されている、
集中力を高める方法「How to Get Your Brain to Focus」が勉強にも仕事にも有益すぎたのでまとめておきます🧠📝⤵︎
1.集中できないのは“怠け”ではなく“刺激過多”が原因
2.スマホを1日30分以内に制限すると注意力が回復
3.“退屈な時間”を意図的につくるとアイデアが湧く
4.心をあえて“さまよわせる時間”が創造力を高める
5.やることより“余白”をつくる方が生産性は上がる
6.「注意の質=人生の質」になる
集中とは「頑張る」ことではなく、
“刺激を減らして脳に余白を与えること”。
スマホを断つことやぼーっとする時間が大切です。
な retweeted
PMの役割が「決定者」から「ファシリテーター」に変わっているというのは本当にそうですよね。
この流れ、実は去年大手企業のAI活用支援をした時に痛感しました。
従来の進め方だと、PMが要件を固めてからエンジニアに渡すという流れだったのが、AIプロダクトでは最初の1週間でプロトタイプを作って実際の出力を見ながら全員で方向性を決め直すことが3回もあった。
ここで重要なのは「失敗を早く共有する文化」を作ること。
具体的には、毎日15分のスタンドアップで「昨日の実験で期待と違った結果」を必ず1人1つ共有するルールを設けた。これだけで手戻りが半分になる。
もう1つ、チームメンバーを必要最小限にするのも大事。4人以下が理想。人数が増えると意思決定が遅くなり、AIの出力品質を見ながらの素早い方向転換ができなくなる。
AI時代のPMは「答えを知っている人」ではなく「チーム全員で最適解を見つけるための問いを投げかけられる人」になる必要がある。
AIプロダクト開発の現場ではPMの役割が大きく変わっている組織が増えてきた。生成AIプロダクトのPMたちの話を聞くと、従来の「要件定義→実装→テスト」という線形の進め方が通用しなくなっているのがよくわかります。どう変わっているのか?
AIの出力品質がプロダクト体験の中心にある以上にFigmaのような静的プロトタイプを見せてユーザーの反応を見るといった従来型のユーザーテストはもはや意味がない。ユーザーは“動的なAIのふるまい”に価値を感じるためその「出力の質」こそが評価の対象になるからです。
そのためPM、エンジニア、デザイナー、そして新たに加わったサイエンティスト(AIリサーチャーやデータサイエンティスト)は、以前よりもはるかに密接に連携するようになっている。モデルの挙動やデータの偏り、ユーザーの期待値と出力のギャップ、こうした複雑な要素を一緒に扱うには職種の垣根を越えた協働が不可欠になった。そのためチームメンバーも必要最小限になることが多い。
例えばエンジニアも単に実装を担うだけでなく、実験設計やユーザー体験の定義にまで踏み込むことが求められている。AI時代のプロダクトでは「コードを書く力」よりも「プロダクトとして何を学習させるかを設計する力」が問われるようになったとも言えますね。そしてPMはチームの中心で全てを決める存在ではなくむしろチームメンバーがそれぞれの専門性を最大限に発揮できるよう環境を整えるファシリテーターへと変化しています。指示を出すのではなく問いを立て、実験を設計し、失敗を早く共有する。そんなチーム運営が成果を左右する時代に入ってきた。
AI時代のPMに求められるのは従来の方向性を決め現時点での最適な解を出す力だけではなく「チームメンバーと密に協業してAIの力を活かす」方向になってきた。より広く・専門性が高い役割になっていくのは間違いない。
な retweeted
古典が大事なのは分かったが、じゃあ何読めばいいの?って方
個人的におすすめの古典を紹介(ビジネス系)
まぁこの辺を抑えとけば間違いないです
【経営戦略】
1.『競争の戦略』
著:マイケル・ポーター
2.『企業戦略論』
著:ジェイ・B・バーニー
【マーケティング】
1.『マーケティング・マネジメント』
著:フィリップ・コトラー
2.『キャズム』
著:ジェフリー・ムーア
【会計 / ファイナンス】
1.『企業価値評価(Valuation)』
著:マッキンゼー&カンパニー
2.『稲盛和夫の実学 経営と会計』
著:稲盛和夫
【組織】
1.『マネジメント』、『現代の経営』
著:ピーター・ドラッカー
2.『学習する組織』
著:ピーター・センゲ
【リーダーシップ】
1.『リーダーシップ論』
著:ジョン・コッター
【イノベーション】
1.『イノベーションのジレンマ』『ジョブ理論』
著:クレイトン・クリステンセン
【思考法】
1.『考える技術・書く技術』
著:バーバラ・ミント
【自己啓発】
1.『7つの習慣』
著:スティーブン・コヴィー
【人生の指南書】
1.『ドラゴンボール』
著:鳥山明
な retweeted
知人がデジタルデトックスを始めてから格段に本が読めるようになったと言っていたが、脳の情報処理が切り替わったということだと思う。
スマホをたくさん見ている状態で本を読むというのは、読みやすい新書やエッセイのような軽い文体のものを除けば、相当な認知負荷に耐えられる人でないと難しい。
スマホの閲覧は短い文脈と多層的な刺激、通知やスクロールといった即時報酬によって成り立っており、主に働いているのは前頭前野ではなく、線条体や前帯状皮質といった報酬系のネットワークだからで、スマホを見ているときの脳は「読む」というより「選ぶ」「判断する」「反応する」を繰り返しており、情報の意味よりも反応速度を優先する状態にある。
本を読むという行為は持続的な注意と内的文脈の保持を必要とし、ワーキングメモリや前頭前野背外側部などの認知制御系が中心に働く。スマホでの情報摂取と読書は神経的にほぼ対立するモードであり、報酬系が過剰に活性化している状態では「すぐに結論が来ない」「理解に時間がかかる」といった読書特有のテンポがストレスとして感じられてしまう。
だから、スマホを多く使っている生活の中で本を深く読むのは、集中できないというより、報酬系と認知制御系の間で干渉が起きているということ。
デジタルデトックスを行うと、この即時報酬サイクルが一時的に遮断され、脳が再び“遅い報酬”を処理できるモードに戻っていく。つまり、読書のように結果がすぐ得られない行為にも快楽を見出せる神経構造が再調律されるということで、本が読めるようになったというのは意志力の問題ではなく、情報摂取様式の神経的再構築の結果に近い。
スマホを長時間使いながらも深く本が読める人は、報酬系の刺激を制御できる非常に強い認知的抑制力を持つか、あるいはスマホ使用中でも情報の浅さに同調しない集中の癖を持っているごく少数の人に限られる。スマホから本への切り替えは「デジタルからアナログへの移行」ではなく、「報酬系から意味系への切り替え」であり、そのモードチェンジには時間とエネルギーを要する。
な retweeted
こちら、ピラティスに対する言語化が素晴らしいです。
ピラティスは決して悪い運動ではないのですが、根本的にピラティス=ダイエットという認識が間違えているんです。
痩せるためには身体を鍛えて代謝をあげて脂肪を燃やすしか無いので、ボディメイクには筋トレが最も効率的で効果的で最強なんです。
ただし強度の調整やメニュー構成、その人の骨格や可動域に合わせたフォーム、日々の食事内容等々が非常に大切となりますので
SNSの情報だけを鵜呑みにせず、知識や経験のあるトレーナーについて教えてもらうことをオススメします。ジム店舗さんやトレーナーさんが発信している情報は良いものが多いかと思いますが、我流でダイエットをしているインフルエンサーさんやネットの情報を詰め込んだだけの投稿にだまされないようにしてください。
あとは骨格的に各部位の肉付きは違いますし、筋肉がつきやすい(つきにくい)箇所も異なります。それは骨格形成の個人差により可動域やパワー、関節の柔軟性が違うからです。
さらに言うならば、骨格だけでなく体質的にも痩せ方や太り方は十人十色に違うので、極論を言うと、最初から痩せやすい人のやっていることをただ真似しても太りやすい人は痩せないですし、どうしても足だけ痩せない人が足を細くしたくても、元々足が太りにくい人の真似をしても同じようにはならないです。
ピラティスが大きく流行り始めた背景には、韓国アイドルなどスタイル抜群な女性たちが取り入れているという視覚的イメージの影響が大きいと思うけど、実際にピラティスを長年行っている人たちを何十人、何百人と見ていると、週に何回も、何年も継続していても、体型や骨格が根本的に変わることはない。姿勢や動きの質が最適化されることはあっても、それは「身体の使い方が洗練される」という神経的な変化であって、骨や筋の形そのものが変わるわけではない。
ピラティスは本来、体型を細くするよりも、神経筋制御を整えるためのメソッドで、姿勢・呼吸・関節の可動パターンを最適化することで、身体を効率よく、無理のない状態で動かせるようにするもので、見た目としては姿勢が良くなったり、ラインが整ったように見えたりするが、それは「整列の結果としての見え方の変化」であって、「体型そのものの変化」ではない。
ピラティスを習慣にしている体型が細い彼女たちはもともと食事のの摂取カロリーを細かく管理し、有酸素運動やダンスで日常的に代謝を上げており、ピラティスはその全体の中の「調整と維持のパート」に過ぎない。細く見えるのは、ピラティスの効果ではなく、食事制御や運動習慣など、別の条件が揃っているからに他ならない。
ピラティスで“痩せる”というのはマーケティング上の再定義であり、実際には「痩せている人がピラティスをしている姿」を見て、あたかもピラティスが痩せさせているように見えている。
ピラティスやボディワークを長く見ていると、結局「理想の姿勢」なんて存在しないと分かってきます。骨格の形、筋の張力、呼吸の癖、重心の置き方、どれも人によって違っていて、それぞれの身体にはそれぞれの調和点がある。その調和点を見つけていくプロセスが「最適化」であり、それが整った瞬間の身体は、必ず静かな美しさを帯びます。
な retweeted
経産省時代、初めてITの部署に着任してから、「ネットワークはなぜつながるのか」「コンピュータはなぜ動くのか」の2冊を読み込みました。決してとっつきやすい本ではないし、挫折者を多数生み出す本だと思いますが、間違いなくその後10年役立つ基礎がつくれます。
「ITの教養」が身につく良書 文系も理系も必読の名著9冊
nikkei.com/article/DGXZQOUD0…
そもそもデジタル化とは何か、コンピューターはどのように動いているのか。「仕組みの基本と全体像の輪郭」が分かる本を、IT系ヒット書籍を手掛けてきた編集者が厳選しました。